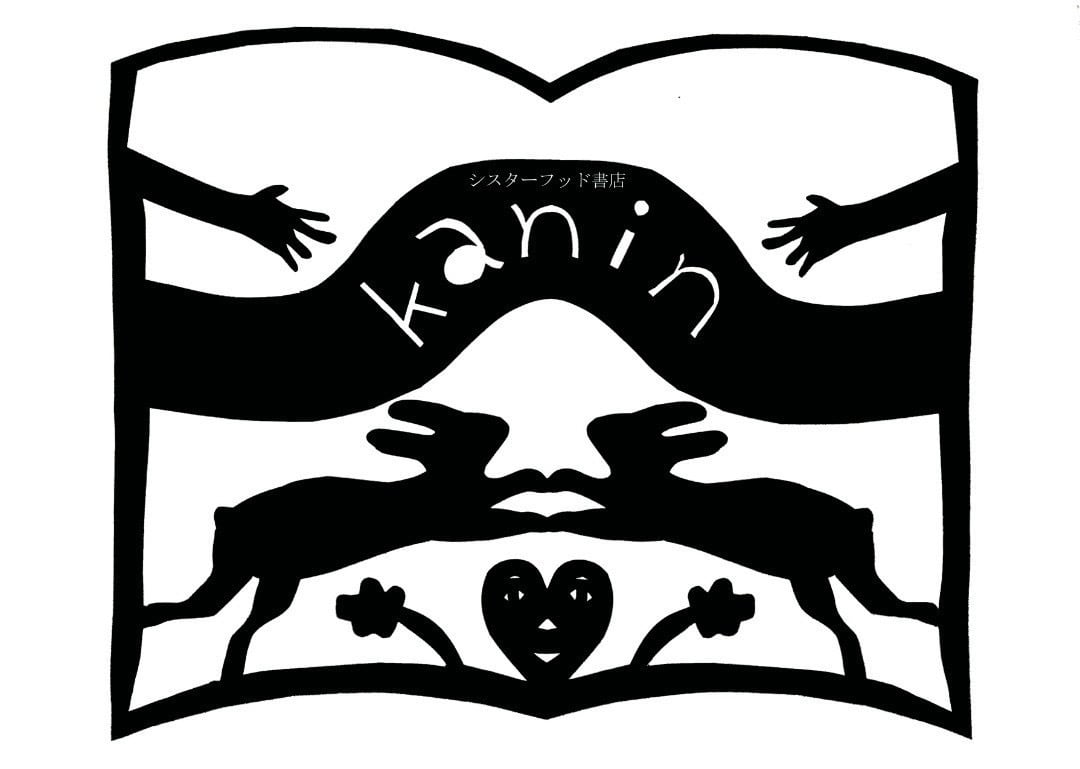-

KaninのZINE『更年期って、つらい?』
¥1,100
総勢17人による更年期体験記。 多くの人が経験する更年期症状なのに、声高に語られないのはなぜ? 更年期を目の当たりにした戸惑いや正直な気持ち、実際に体験し、くぐり抜けてきたこと。それらをおおっぴらに語ることで、社会的に見えなくされがちな中高年女性たちの存在を可視化したZINE。 〈目次〉 はじめに 更年期反乱軍の変 〈飛鳥純〉 更年期、矛盾を抱えて生きる 〈井元あや〉 イライラしすぎて顔が四角くなり、髪が抜けて頭皮に穴が開く 〈てまり〉 「更年期ってつらい?」と聞かれたら 〈CHOMEL〉 更年期は便利 〈アバ〉 もっと自分を甘やかす 〈山田ナミオ〉 更年期の先に 〈ことり〉 更年期~わたしの場合~ 〈おはしおき〉 更年期に片足突っ込んでいるらしい 〈藤崎殊海〉 てんこ盛りいただきました 〈ケトヤ〉 セカンド・シーズン 〈さくらいたまみ〉 更年期 若きシスターたちへのメッセージ 〈よねかわかずこ〉 選ぶこと抵抗すること 〈野良〉 For fanden! 男性更年期 〈京極祥江〉 更年期、病院の村社会にふりまわされる。〈西森路代〉 更年期と鬱病と。 〈森山りんこ〉 ホルモンが枯渇しています―更年期と膣炎と膣座薬とー 〈吉良佳奈江〉 店主2人の更年期対談
-

KaninのZINE『女ひとりで、生きる』
¥1,100
Kanin4冊目のZINE(新刊です)。 非正規雇用が多く、賃金も男性に比べると低い女性。「結婚しないのか」「離婚した人はかわいそう」「子どもを産まないなんて、老後はどうするんだ」という社会的プレッシャーもまだまだある中で、「女がひとりで生きていく」のは大変なことです。 それでも、ひとりで生きることを選んだのはなぜ? ひとりで生きると決めた理由、ひとりで生きていく中で感じたモヤモヤ、怒り、不安、喜び、希望などを描いたエッセイ集。
-

KaninのZINE『離婚って、ふしあわせ?』
¥1,100
Kanin初めてのZINE『離婚って、ふしあわせ?』。 離婚当事者、別々に生きていく選択をした両親を持つ人、親が再婚を決めた子、未婚の人……さまざまな背景を持つ13人が「離婚」について語ったエッセイアンソロジー。 A5版・64ページ <執筆者一覧(掲載順・敬称略)> UNI(うに) 井元あや(シスターフッド書店Kanin 店主©) ほんだな アヤ 犬飼愛生 イヌコ COOKIEHEAD バーヌ 市川桜子 うちねこ 若林理央 京極祥江(シスターフッド書店Kanin 店主S) 横田祐美子
-

KaninのZINE『私たち、氷河期世代』
¥1,100
Kanin2冊目のZINE『私たち、氷河期世代』。「氷河期世代」に属する人たち22人が語る人生の軌跡。文学フリマ京都出店にあわせて発売。 A5版・104ページ <執筆者一覧(掲載順・敬称略)> 橋本いくら 京極祥江(シスターフッド書店Kanin 店主S) tiny 葱山紫蘇子 ぽんつく オータ 桜庭紀子 大塚文 てまり ゴンタ 野田茜 板垣ちはる そよ 寺橋佳央 Maico ドタバタキャリぽん 伊勢村朱音 奏果 山内美佐 言来あさ 柳川麻衣 井元あや(シスターフッド書店Kanin 店主©)
-

KaninのZINE『シスターフッド書店Kaninができるまで』
¥1,100
シスターフッド書店Kaninの店主2人が小学校で出会ってから、ふたりで書店を開くまでにいたった経緯を語るZINE。ご要望におこたえして(?)、文学フリマ京都出店にあわせて発売! B6版 68ページ
-

新刊『ポストフェミニズムの夢から醒めて』 菊地夏野 著
¥2,640
フェミニズムは終わらない、いや終わりようがない フェミニズムの終焉をかたる「ポストフェミニズム」の時代を経て、私たちは再びその盛り上がりに立ち会っているといわれる。だがそこで喧伝される「新しいフェミニズム」の実像と、その向かう先は果たしてどこまで理解されているだろうか。ネオリベラリズムと結託した「リーン・イン」や「女性活躍」の欺瞞を問い、セックスワーカーやトランスジェンダーへの差別、「慰安婦」問題などそこからこぼれ落ちるものにまなざしを向けることで、見えてくるものとは。フェミニズムをあきらめないための、たしかなる提言。 line2.gif [目次] まえがき Ⅰ ポストフェミニズムの時代に可視化されるもの 第1章 憧れと絶望に世界を引き裂くポストフェミニズム――「リーン・イン」、女性活躍、『さよならミニスカート』 第2章 ポストフェミニズムとネオリベラリズム――フェミニズムは終わったのか 第3章 ネオリベラルな家父長制と女性に対する暴力 第4章 可視化するフェミニズムと見えない絶望――ポストフェミニズムにおける(再)節合に向けて 第5章 ポストフェミニズムから99%のためのフェミニズムへ 第6章 『逃げ恥』に観るポストフェミニズム――結婚/コンフルエント・ラブ/パートナーシップという幻想 Ⅱ 不可視化されるものとフェミニズムの未来 「雑多なフェミニズム」をめざして―第二部へのはしがきに代えて 第7章 「慰安婦」を忘却させる植民地主義とポストフェミニズム――『帝国の慰安婦』、スピヴァク、ポストコロニアル 第8章 フェミニズムは右傾化したのか?――ネオリベラル・フェミニズムの世界 第9章 AV新法をめぐるフェミニズムの混乱 第10章 安倍/統一教会問題に見るネオリベラル家父長制――反ジェンダー運動とネオリベラリズムの二重奏 第11章 99%のためのフェミニズムと私たち 第12章 リーン・イン・フェミニズム批判と田中美津の〈どこにもいない女〉 終章 「#MeToo」と「Ni Una Menos」から あとがき 文献
-

新本『女性と図書館―ジェンダー視点から見る過去・現在・未来』(青木玲子・赤瀬美穂著)
¥2,970
明治期から現在までの図書館は女性にどのようなサービスや資料提供を行ったかをジェンダーの観点から文献により検証・考察した一冊。戦前に存在した婦人閲覧室や戦後に設立された男女共同参画センター・女性情報ライブラリーについて取り上げ、その存在意義を再確認できる。日本の図書館におけるジェンダー問題を可視化し、関連資料提供の際のヒントに。「索引」付き。
-

新刊『エキストリーム・センター』(酒井隆史・山下雄大編)
¥3,520
「中道がファシズムを準備する」 エキストリーム・センター(極中道)とは何か? なぜこの現象を問わなければならないか? フランスで「エキストリーム・センター」という批判概念を編み出し、またたくまに世界に広めたピエール・セルナ(Pierre Serna)が直接寄稿。ほか、デヴィッド・グレーバーの「中道」論、アルベルト・トスカーノの「ファシズム」論など、選りすぐりの10本の論文を掲載。現代政治・現代社会の激変を読み解くカギがここにある。 日本初の「エキセン」論集かつ決定版。
-

新本『日本のヤバい女の子』(はらだ有彩著、名久井直子 装丁)
¥1,540
日本の神話や古典、民話を、登場する女性の心情に寄り添いながら大胆かつファンキーに読み解く、新感覚のイラストエッセイ。
-

新刊『をとめよ素晴らしき人生を得よ』(瀬戸夏子著)
¥2,090
注目を集めたウェブ連載に、 書き下ろしを加えた待望の書籍化。 語られてこなかった女性歌人たちのレジスタンスを、 現代によみがえらせる。 『はつなつみずうみ分光器』の著者が挑む、 女たちの群像伝記エッセイ。
-

新刊『資本主義の敵』チョン・ジア 著 橋本 智保 訳
¥2,420
「ここに資本主義の真の敵がいる。 かつて社会主義を信奉した私の両親のことではない。 資本主義の動力である欲望を否定する者たちだ。」 純文学と諧謔的コメディが交錯するなかで実存的な問いを鋭く掘り下げた傑作短篇集。 発禁作『パルチザンの娘』でデビューし、『父の革命日誌』が韓国で30万部を超す大ベストセラーを記録した、孤高の女性作家の真骨頂。 〈両親の足跡をたどる『パルチザンの娘』によって一躍その名を世に知らしめた数年後、小説家としてデビューを果たしたチョン・ジアは、短編小説という形式の中で両親の記憶を掘り起こし、積み重ねながら、その存在論的な問いを求礼という土地と結びつけて描いてきた。彼女の過去の作品には自伝的な要素が色濃く反映されており、分断国家がもたらしたイデオロギーに苦しむ登場人物たちは、その連鎖から逃れることができず、むしろそれによってのみ自己の存在を証明しうるかのように描かれていた。求礼に暮らす隣人たちもまた、それぞれ異なる物語を抱えて生きている。他者の声に耳を傾けること、多様な存在のありようを見つめる眼差しこそが、この短編集に見られる変化なのではないか。——訳者〉 《たいていの読者は、チョン・ジアという名前から「パルチザンの娘」を連想するだろう。 気持ち? そんなものクソくらえだ。 私が生まれたとき両親はすでに年老いており、資本主義の死んだ敵にすぎなかった。 社会主義という四文字は私の人生の記憶に烙印のごとく刻み込まれ、その敵である資本主義に対しては並々ならぬ関心を持つことを余儀なくされたのだ。クソったれ。》 装画:イシサカゴロウ
-

新刊『地方女子たちの選択』(上野千鶴子、山内マリコ 著)
¥1,980
「地方の女性流出」が取り沙汰される今日だが、当の女性たちの姿はあまり見えない。それは女性が減ると産まれる子どもの数が減るという、「数」でしか見られていないからだろう。 本書では、地方都市のひとつ富山で女性14人の語りを聞き取り、「数」から「生身のある人間」へと解像度をあげた。彼女たちはなにを選んできたのか、選べなかったのか。語りを通して、みえてくるものとは。 「富山から出ていく」選択をした上野千鶴子と山内マリコが、様々な選択が幾重にも交錯する語りをふまえ、対談し、地方をみつめなおす。
-

新刊『「ソロ」という選択』(ピーター・マグロウ著、江口泰子訳)
¥3,080
ひとりがダメだなんて誰が決めた! 社会は結婚を前提にできていて、独身者向けの本はいいパートナーを見つける方法ばかり……でも、それって本当に自分にとって必要なことなの? ソロ・プロジェクトを唱導する著者が、ひとりでいることの喜び、社会性、充実感、そして規則にしばられない最高に幸せな人生の送りかたを教えてくれる。そうだ、自分は自分のままでいいんだと勇気づけられる。ひとりの人も、パートナーがいる人も、ここから「ソロ」をはじめよう。
-

新刊『日本 「完璧」な国の裏側』(西村カリン著、村松恭平訳)
¥2,420
SOLD OUT
政治、メディア、安全、司法、家父長制、教育、高齢化、働き方、移民… 日本で暮らす“闘うフランス人記者”西村カリンが炙り出す、この国の姿。 「日本はすべてに成功したのだ。見かけ上は」 フランスに生まれ、日仏のメディアで働きながら日本社会を見つめ続けてきた著者は、官邸の記者会見やテレビ番組のコメンテーター等、鋭い観察と発言で注目を集めてきた。 本書では、現代日本が抱えるさまざまなテーマに切り込み、海外の視点からは「完璧」とされがちな日本のイメージの裏側にある構造的な問題を描く。扱うテーマは、政治、メディア、安全、司法、社会的関係、家父長制、教育、高齢化、 働き方、移民、ポピュラーカルチャーなど多岐にわたり、フランスを中心とした国際的な比較も織り交ぜ、日本社会の特異性と善悪両面を炙り出す。
-

新刊『独裁者の倒し方: 暴君たちの実は危うい権力構造』(マーセル・ディルサス著、柴田裕之訳)
¥2,420
「世界の厄介者」はなぜ倒れないのか? 側近たちとの避けられないトレードオフ、非道な行動の背後にある、裏切りや暗殺、叛乱への恐怖…… 独裁政権の特異なパワーバランスや脆弱性を明らかにし、抑圧なき世界を実現するための書。 「思考を喚起する」--エコノミスト紙 「圧倒される」--フィナンシャル・タイムズ紙 「愉しく読める」--デイリー・テレグラフ紙 「完全に引き込まれる」--ブライアン・クラース(『なぜ悪人が上に立つのか』著者) エコノミスト紙「2024年度ベストブック」に選出、世界20カ国で刊行! 独裁者は側近がつくる。 独裁者になるということは、降りられないランニングマシンの上で走り続けるようなものだ。 彼らはその立場上、「穏やかに辞任する」という出口戦略を持ちえず、常に脅威にさらされているのだ。 政権のパワーゲームという視点で独裁制を読み解く画期的な書。
-

新刊『シモーヌ2026年冬号』
¥1,980
【特集1】フェミニズムから見たやまゆり園事件とその後の10年 鶴峰まや子 終わらない問いに応え続ける 東風ゆば やまゆり園事件について語れないはざまの私 堅田香緒里×白崎朝子×向山夏奈 [座談会]ケアワーク視点で振り返るやまゆり園事件 稲原美苗 「家族愛」に潜むケアの課題:フェミニズムと現象学の交差点から 土屋葉 ジェンダー視点で振り返る旧優生保護法:否定された性 近藤銀河 殺されない者による映画『月』批評:あるいは差別のある社会によろめきながら抵抗すること 栗田隆子 怠け者フェミニストの視点から考える「生産性」と「労働」 船本淑恵 国連障害者権利委員会「総括所見」と知的障害者福祉施策の展開 坂上香 交差性(インターセクショナリティ)としての「津久井やまゆり園事件」 【特集2】買春処罰は誰のため? 青山薫 買春処罰のリアリティ:なぜ、いま、日本で? アリソン・フィップス 訳:firda people なぜ「北欧モデル」が最悪なのか(参考資料を添えて) エレン・ルバイ、カロジェロ・ジャメッタ 訳:frida people セックスワーカーはフランスの売春法をどう考えているか? あかたちかこ 「そこに人がいる」本当に、ただそれだけのこと 戸谷知尋 「Dignity by Design」に参加して:ヨーロッパにおけるセックスワークの法政策の議論 飯田麻結 「選択的共感」に抗う:セックスワーク・情動・新自由主義 ニーナ・ヴオラヤルヴィ 訳:戸谷知尋 買春者の犯罪化:北欧地域の経験から シャルレーヌ・カルデラーロ、カロジェロ・ジャメッタ 訳:花岡奈央 「売春問題」:フランスにおける移民管理・公共秩序・女性の権利の名のもとに行われる抑圧的な政策 【連載】 宮田りりぃ セックスワーカー視点のセクシュアルヘルス ヨヨミ ヘルシー♡メルシー ドレヤ MUSIC SPOTLIGHT WE ARE HERE. WE ARE EVERYWHERE. yonieの日記 げいまきまきのワイルド・サイドを歩け! SWASHのSLUTS GO EVERYWHERE
-

新刊『「自分のかたち」のまま、これからも私は 』(貝津美里著)
¥1,760
なんで私のことなのに私が決めちゃだめなの? なんで私は私なのに変わらなくちゃだめなの? ――選択肢は、「自分の身体」を生きる “あらゆる”女性の言葉の中に。 28歳。 ある出来事で自身の価値観が揺らいだ著者は、「『自分らしく』生きるとは何か」を問い直すため、カナダへ。 多様性が尊重され、LQBTQ+の権利が法律で守られ、首相がフェミニズムを語る国には、日本を出て自分自身で選んだ道を軽やかに進む人たちの姿があった。そんな人たちの葛藤と選択を記録したノンフィクション。 この本の中には今、モヤモヤを抱え、「普通」に縛られ、人生の岐路に立つあなたの選択肢を広げてくれる言葉が、必ずあります。
-

新刊『男と女とチェーンソー──現代ホラー映画におけるジェンダー』(キャロル・J・クローヴァー著、小島朋美訳)
¥3,300
なぜ女は逃げ、叫び、そして生き残るのか? なぜ男は女を追い、殺し、そして見つめるのか? 『悪魔のいけにえ』『ハロウィン』『13日の金曜日』など、ホラー映画史を代表する作品群を通して、現代社会における性と権力の神話と構造を照らし出す。ホラー研究、フェミニズム批評、さらにはファン文化にも大きな影響を与えた記念碑的著作。 「本書の目的は、ホラー映画の観客そのものについての研究ではないし、ホラー映画というジャンルそのものについての考察でもない。本書が探求するのは、「観客の多数派」(若い男性)と、特定のホラー映画において際立つ女性のヴィクティム゠ヒーローとの関係である。この組み合わせは、映画観賞という行為そのものについて、そして表象のポリティクス、転移のポリティクス、さらには批評と理論のポリティクスに関しても、多くの示唆を与えてくれるものだと私は考えている」(本書より)
-

新刊『男も女もみんなフェミニストでなきゃ(文庫版)』チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ著、くぼたのぞみ訳
¥880
SOLD OUT
わたしはハッピー・フェミニスト! ビヨンセを始め全米が称賛したTEDスピーチ、待望の邦訳! あたらしいジェンダーについて最適の1冊。 小説の名手、チママンダ・ンゴズィ・アディーチェが、自らの体験をもとに考察をめぐらせ、「フェミニズムはみんなのもの」と説いています。TEDのスピーチが基なので話し言葉で分かりやすく、読みやすい。フェミニズム入門書としてぴったりだと思います。 余談ですがチママンダ・ンゴズィ・アディーチェの小説は本当に名作ぞろい。『半分のぼった黄色い太陽』は号泣必須、『アメリカーナ』ではすれ違う男女の思いと人生が切なく、とにかくどの本もすべて面白いのでぜひ読んでいただきたいです。(店主S)
-

新本『キャリバンと魔女』シルヴィア・フェデリーチ 著 小田原琳・後藤あゆみ 訳
¥5,060
SOLD OUT
ジェンダーとは階級である 16、17世紀の欧米を席巻した魔女狩りによって迫害・処刑された女性たちとその身体こそ、〈資本主義〉が恐れ、強制的に統治しなければならなかった存在であり、シェイクスピアの戯曲『嵐(テンペスト)』に登場するキャリバンこそ、資本主義が生んだ植民地支配への象徴的な抵抗者だった……。 「家事労働に賃金を!」のスローガンを掲げ、フェミニズム運動の中心的活動家のひとりであるシルヴィア・フェデリーチは膨大な歴史資料・民族誌の読解を通じて、マルクスの本源的蓄積、フーコーの身体論を批判的に検討。彼らが描ききれなかった魔女狩りから植民地支配、今日のグローバルな規模で実施されるIMF・世界銀行の構造調整プログラムによる搾取を、資本主義による女性への暴力と支配の歴史として、フェミニストの視点から書き換える意欲作。
-

新本『台湾ホモナショナリズム 「誇らしい」同性婚と「よいクィア」をめぐる22人の語り』松田英亮 著
¥1,980
台湾は本当に「LGBTユートピア」なのか? 22人のマイノリティの語りに向き合い読み解かれる、 揺れ動く台湾の実相と、いくつもの〈性/生〉の「現在地」 「台湾のホモナショナリズムとは、共同体としての異性愛規範は維持しつつ、台湾をアジアにおいて例外的に「同性愛に寛容」な場とし、(…)国家・文化的な優位性を特徴付ける形で、同性愛者を国家に内包する言説」であると同時に「「台湾という存在自体」を維持することに寄与している」── (本書「おわりに」より)
-

新本『ブラック・スワンズ』イヴ・バビッツ 著 山崎まどか 訳
¥3,080
SOLD OUT
イヴ・バビッツの文章のほぼ唯一の欠点は、読んでいるともう彼女の文章しか読みたくなくなるところにあるーー山崎まどか 血眼で駐車場を探して、ロデオ・ドライヴをひやかして、アルゼンチンタンゴにハマって、ヴァンパイアみたいに美しい男とシャトー・マーモントに入り浸って、L.A.いち古いレストランで友達とブランチを食べて、しゃべって。 華やかなりしL.A.の申し子で恋人。彼女のレンズを通したら、この街はひどく美しくてどうしようもなく愛おしい、故郷《ふるさと》だ。 鋭い観察眼とキレのあるユーモアでジョーン・ディディオンとならび称される作家、イヴ・バビッツがL.A.を行き交う友人たちをモデルに描いた短編集、待望の初邦訳!
-

新刊『「あの選挙」はなんだったのか 2024衆院選・2025参院選を読み解く』 荻上 チキ 編著
¥2,200
執筆者:荻上チキ/飯田 健/菅原 琢/秦 正樹/三牧聖子/能條桃子/辻 愛沙子/中村知世/安田菜津紀/永井玲衣(掲載順) 2024年衆院選と2025年参院選、「あの選挙」は一体なんだったのか? 民主党政権を挟みながらも、自公政権が長く続いてきた日本政治。2024年の衆院選では、与党が過半数を割るという大きな変化が起こった。この変化は、期待されていたような「政権交代への作用」を実際に生み出したのだろうか。驚きや戸惑い、さらには予想外の熱気など、様々な反応がみられるなかで、「あの選挙」の結果と過程から何を学び、どのように理解すべきなのか。その全体像はいまだにみえていない。 国民民主党の躍進、立憲民主党の伸び悩み、日本維新の会の凋落、参政党の急速な伸長、多様化する少数政党、そして自民党と公明党の連立与党の衆参両院での過半数割れによって生まれた新たな政権の枠組み。いまの政治状況は、本当に国民が望んだものであり、「民意」が反映された結果なのだろうか。 ・「あの選挙」で起こったこと/起こらなかったこと ・「あの選挙」で変わってしまったこと/変わらなかったこと ・「あの選挙」で届いた声/届かなかった声…… 選挙のたびに入れ替わる、注目政党や選挙手法のトレンド。目まぐるしく変わる状況を前に一度立ち止まり、考え、対話するための土台となる知見を、政治学、データ分析、アメリカ政治、ジェンダー平等、SNSマーケティング、ジャーナリズム、哲学対話の専門家たちがそれぞれの視点から解説。そして、そこからみえる「民意」の本当の姿とは。 「あの選挙」から「次の選挙」へ進んでいくために。 いまだからこそ知っておきたい、すべての世代に向けた選挙の新しい入門書の第2弾。 目次 まえがき 荻上チキ 第1章 自民党はなぜ負けたのか?――消えた小選挙区ボーナスと有権者のリスク認識 飯田 健 1 自民党票の行方 2 消えた小選挙区ボーナス 3 暮らし向き評価と自民党離反 4 悲観的な暮らし向きの見通しと政党のリスク認識 第2章 並立制はどのように日本政治の混迷を深めたのか?――二〇二四年衆院選・与野党逆転の計量分析 菅原 琢 1 衆院並立制と政党政治 2 比例区の多党化と小選挙区の与野党逆転――二〇二四年衆院選結果の概略 3 激化した野党間の候補者の競合 4 立憲民主党候補を支えた国民民主党の党勢拡大 5 共産党大量擁立の影響の評価 6 小選挙区で不利な国民民主党 7 再考を迫られる並立制 第3章 誰が野党を支持しているのか?――脅かされる立憲民主党と躍進する「第三極」 秦 正樹 1 日本政治の分岐点としての二〇二四年衆院選 2 比較のなかの二〇二四年衆院選 3 「立憲民主党の伸び悩み」を科学する 4 新たなステージへ向かう野党 第4章 なぜ民主党は負けたのか?――二〇二四年アメリカ大統領選挙にみるリベラルの敗因 三牧聖子 1 二〇二四年大統領選トランプ再選の衝撃 2 「変化」を訴えられなかったハリス 3 「リベラル」から後退していったハリス 4 気候変動対策で後退したハリス 5 トランプを「平和」の候補にみせたガザ政策の失敗 コラム1 女性が選挙に立候補するとはどういうことか?――「FIFTYS PROJECT ワークショップ報告書 統一地方選挙に出馬した女性候補者が体験した制度課題および社会課題についての調査」をもとに 能條桃子 第5章 いま、メディアは選挙をどう動かしているのか? 辻 愛沙子/荻上チキ 1 選挙とインターネットというメディア 2 選挙を動かしたのはどのメディアだったのか 第6章 二〇二五年参院選は誰が勝ったのか?――日本政治の新たな局面 秦 正樹 1 二〇二五年参院選は「日本政治の転換点」か 2 世論における二〇二五年参院選の意味 3 二〇二五年参院選は誰が「勝った」のか 4 日本政治の新局面としての二〇二五年参院選 第7章 参政党の「躍進」はなぜ起きたのか?――都議選参政党投票者への追跡調査から 荻上チキ/中村知世 1 参政党支持者の基本属性 2 参政党を支持しつづけた人/離脱した人 3 ファクトチェックとメディア接触の影響 4 参政党支持者と外国人嫌悪 5 「YouTube」と陰謀論の親和性 6 参政党支持とは何か コラム2 選挙はマイノリティーの声を聞くことができているか? 安田菜津紀 第8章 選挙を考えるとはどういうことなのか?――政治と社会と暮らしをめぐる哲学対話 永井玲衣 あとがき 荻上チキ
-

『彼女は何を視ているのか』(竹村和子著)
¥8,000
SOLD OUT
私たちの性意識や欲望は、映像・映画によっていかに創られているのか? 惜しくも急逝した、日本を代表する批評理論家・竹村和子が、その理論・思想を映像分析に応用した、挑戦的ジェンダー映画論。 トリン・ミンハとの対話、レイ・チョウ、ローラ・マルビィとの対論も収録。